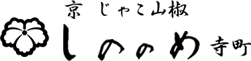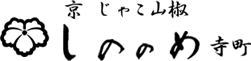味 2
店のこと
2016年11月10日

今回はちょっと自慢を…。
いろいろな店のおじゃこを買い集めて食べ比べをするんだよ、なんて話してくださるお客様が時々いらっしゃいます。そんななかのお一人、京都のちりめん山椒については自称第一人者、と名乗られる写真の男性。「ちりめん山椒食べ比べグランプリ」なるものを、お仲間内で開催されています。前回のご来店時に、これから3回目をやります、と仰ってお買い上げ。緊張しながら商品を手渡したのを覚えています。http://sakura394.jp/holiday/food/chirimen-gp2016
この大会、店名を伏せて行われます。まさに味勝負。結果、なんと「しののめ寺町」が二連覇とのこと。名古屋から賞品を携え、報告にお越しくださいました。賞品は名古屋名物えびせんべい「ゆかり」。豪華な包装紙が、まるで金の延べ板のよう(笑)。遊び心いっぱいの演出に、センスが光ります。 http://sakura394.jp/holiday/trip/shinonome3
このことをフェイスブックで報告すると「グランプリ」のイメージが衝撃的だったもよう。とんでもない栄冠を手にしたと思ってくださったお客様や知人から「おめでとう!」のコメントが次々と(汗)。
そんな大それたものではない、なんて言うと主催者の方に失礼でもあり、イメージのままにしているところです(笑)。実際のところ、一般の方がふつうに召し上がって、ふつうに「おいしい!」と仰ってくださる。それは、なににも代えがたい喜び。どんな有名なタイトルより栄誉なことだと思っています!
改めまして、うちのじゃこ山椒、我が家の長男が炊いております。開店初日から一日も欠かすことなく。この賞はまさに彼のもの! なのですが、私と違って控えめなもので、写真はNG。母の代理受賞となりました(笑)。
思い起こせば…。40年前、北区にある「しののめ」を、夫の母が創業。以来、長年にわたり親族で営業してきました。私たちの自宅もそのすぐ近所。長男が幼稚園に通う頃、朝、送って行く途中に、店に声をかけるのが習慣でした。見送りに出てくる義母の指先には、炊き上がったばかりのおじゃこがひとつまみ。見る間に長男の口に放り込まれ、「行っといで!」と送り出されるのが、いつからかお決まりの儀式に。
されるがままに、毎朝、おじゃこを食べながら通園していた長男。しばらく口の中からおじゃこの味が消えないのでは。あとで喉が渇かないかな。なんて心配する私をよそに、嫌がる風でもない様子。まんざらでもなかったのでしょうか。
その長男が、今度はおじゃこを炊く側に。幼い頃に身に着いた味覚は、大人になっても基本となるものです。いつかこんな日が来ることを見越して、義母は孫である長男にこの味を覚え込まそうとしていたのかも、なんて今になって思ったり。開店一年後に亡くなった義母、もう確かめる術はありませんが。
ちりめんじゃこは自然のもの。時々で、塩加減、乾燥の具合などが変わります。出来るだけ変わらぬ状態のものを厳選して仕入れていますが、やはり限界があります。そこを見極めて調整し、同じ味に炊き上がるよう、日々、苦心しているようです。その基準となっているのは、幼い日、毎朝、口に放り込まれたおじゃこの味なのでは、と想像します。
開店から4年半。今なお「元のお店と同じ味ですか ? 」と、日に何度も確認されることがあります。以前のブログでも触れましたが(ブログ味 ブログじゃこ桜)、自分たちなりの最善の仕事が、そのものとして評価されない辛さ。独立した店の宿命と理解しながらも、葛藤の日々でした。
この大会、そのあたりも詳細に比較してくださっています。第三者ならではの客観的視点。それも京都のおじゃこをこよなく愛される方による繊細な分析。私たちにとっても、とても参考になる、有り難い報告でした。http://sakura394.jp/holiday/food/shinonome2
そろそろ、これが「しののめ寺町」の味! と、胸を張ってもいいのかな。生意気ながら、そんな自信を与えてくださった、このグランプリ。感謝の思いでいっぱいです。と共に、これから一層、心して取り組んでいかなければと、身の引き締まる思いも。
たかが、おじゃこ。されど、おじゃこ。こんなにも大真面目に、こんなにも楽しげに、おじゃこを味わってくださるお客様がある。人生、おもしろいものだなぁ。なんて…、最後はおじゃこを超えて、しみじみ思った私でありました。
國立拓治様、本当にありがとうございました!
二葉タクシー
心と体のこと
2016年10月25日

先日、偶然乗ったタクシー。三つ葉のマークでお馴染みのヤサカタクシーさん。車体の色も緑の葉っぱも変わらないのですが、なんだか様子が違います。ほんの数台、四つ葉のマークがあると聞きますが、それとも違う。
京都の三大祭りの一つ、葵祭で行列の皆さんが身に着けられる二葉葵(ふたばあおい)のような。運転手さんによると、上賀茂神社の式年遷宮に合わせた期間限定の車だとか。レシートを上賀茂神社に持っていくと、記念品をいただけるとのこと。大切に財布にしまって降りました。

上賀茂神社までは自宅からは自転車で10分ほど。定休日の先日、陽気に誘われ出かけてみることにしました。わずかの距離ですが、久しぶりに走る賀茂川沿いのサイクリングは、やっぱり気持ちいい。着くとさっそくお札授与所へ。ワクワクしながらレシートを巫女さんに渡すと…。差し出されたのは5cmほどのステッカー。
ちっちゃ~い!
いえいえ、大きさの問題ではないですね。ありがたく頂戴しました(笑)。
上賀茂神社は実家からも近く、以前はよく訪れた場所です。高校生の頃、お正月に巫女さんのアルバイトをしたことも。結婚し、子供が生まれてからは、お宮参り、七五三。店を始めるまでは、初詣は決まってここでした。懐かしくて、ちょっと散策してみることに。

陽射しが暑い日でした。境内のはずれを流れる小川の木陰で、ちょとひと休み。二人のこどもが小さい頃、夏になると水遊びに来た場所です。無邪気に遊ぶ、幼い日の二人の姿が浮かぶよう。その様子を眺めながら、慌ただしい日常から離れ、穏やかな気持ちになっている、若い日の私の姿もそこにあるような。
早くに結婚、出産した私。本当に未熟な子育てでした。今なら、もう少し違った対応ができたろうにと胸痛むことばかり。それでも、その時はそれが精いっぱい。それはそれで一生懸命やっていたんだなぁ。
よくがんばりました、私…。そんな言葉が口をついて出ました。
聞こえてくるのは、川のせせらぎと木々のそよぐ音だけ。こんな音を聞くのは何年ぶりでしょう。境内からほんの数メートル歩いただけで、こんな静寂があるなんて。目を閉じると、自分が限りなく透明になっていく気がします。
思い返せば、子育てに限らず、よくやったと思うことよりも、なにをやっていたんだろうと思うことばかり。後悔することは尽きません。時にそんな自分を責めることも。けれど、もう全部、許してやってもいいんじゃないか。そんな思いが湧いてきました。
川のせせらぎと木々のそよぐ音に合わせて、長年、溜めこんでいた澱(おり)が流れ、そうして消えていくような。いただいたステッカーを改めて見てみると、二葉葵は神との出会い幸せを呼ぶ…と書いてあります。
ああ、今、私は神様と出会ったんだ。
日々の慌ただしさに紛れ、なかなか気づけずにいるけれど、神様はいつも身近にいらっしゃるのかもしれません。二葉葵に導かれ、敢えては作れない時間を作り、出向かない場所に出向き、そこで神様に出会えたこと。それがすなわちご利益だったのでしょう。不思議な不思議な時間でした。
ちなみにネットで調べてみると、ヤサカタクシー1400台中、四つ葉は4台。二葉葵は2台とのこと。クジ運などおおよそ縁のない私が、なぜ ? ! あとになって鳥肌が立ちました(笑)。
イリーナ・メジューエワさんのこと3
アートなこと
2016年10月05日

先月のこと、ロシアのピアニスト、イリーナ・メジューエワさんのリサイタルに出かけてきました。イリーナさんのことは、このブログでも何度か書いていますが、「しののめ寺町」開店当初からご贔屓いただいている、素敵なお客様のお一人です(ブログイリーナ・メジューエワさんのこと)。
クラッシックには興味のなかった私ですが、イリーナさんのピアノは特別。そのときどきに新鮮な感覚が湧き起こり、演奏はもとより、そうした自分の反応をいつもおもしろく思っています。4度目になる今回はどんな自分に出会えるか、ワクワクしながら出かけて行きました。
今回のプログラムはショパン。といって、私に解説ができるわけはありませんが(汗)。これまでは華奢な姿からは想像できない力強い演奏が印象的でしたが、今回はイリーナさんらしい可憐なイメージが際立っていたような。あくまでも個人の感想ですが(笑)。
心で感じたことが、映像となって頭に浮かぶという変な性癖(?)のある私。前々回のリサイタルでは、固かった大地が耕され、その下から現れた柔らかい土に雨が沁み込む絵が浮かびました。その時のブログでは、英語で文化(culture)と農業(agriculture)に同じ文字が含まれることが腑に落ちた。なんてことを書きました(ブログイリーナ・メジューエワさんのこと2)。
今回もまた、柔らかく耕された土に、雨が深く沁みこむ絵が浮かびました。折しも雨続きの日々。雨音を聞き慣れた耳に、ピアノの音色が心地よく重なるようでした。
もう何年前になるでしょうか。まだ店を始める前、といってそう遠い昔ではないころ…。感情があまり動かない時期がありました。感情が動くとしんどくなってしまうのか、防御反応として感情のセンサーがスイッチを切ってしまったようでした。知人の葬儀でさめざめと泣く友人たちに交じり、涙ひとつ出なかった私のばつが悪かったこと…。
そのころ目の前にあった映像はというと、乾燥しきって固くひび割れた土、ところどころ割れ目から伸びるわずかばかりの草…。ただただ広がる荒野の絵でした。感情など持っていたら、とてもじゃないけれど、このなかを進んで行くことはできない。呆然としながらも、妙な覚悟を決めて眺めている自分がいました。
開店を機に、たくさんの方に出会い、たくさんの経験をしてきました。気づけば固かった土はほぐれ、果てしないばかりだった荒野は、緑生い茂る沃土に。今や、うれしいにつけ、悲しいにつけ、ところ構わず泣いてしまう私。感情のセンサーはフル稼働です。
喜怒哀楽を感じることは、案外、体力気力の要るものです。ましてや悲しさやさみしさを感じるのは、ただでさえ辛いこと。それでも、うれしいことはうれしいと、悲しいことは悲しいと感じられるのは、それだけで素晴らしいことなのだと、今、思います。
あらゆる感情を受け止められる、柔らかで豊かな土壌を持った私でありたい。
今回、演奏のなかでポロン、と一音を奏でられることが何度かありました。その一音のなんと美しかったこと。イリーナさんの人生と感性のすべてを込められたポロン。ほかの誰でもないイリーナさんのポロン。静まり返ったホールに余韻を残して消え入るポロン。渾身の一音。渾身の一滴。慈雨のように私の心に深く沁みこんでいきました。
この音のつながりがメロディーになり、曲になる。音楽の素養がないなどと構えることなく、この音を楽しめばいいのだと思いました。音を楽しむ…まさに「音楽」じゃないかと気づき、心の中でひとり手を打った次第です。
ピアノにも楽しげな音、悲しげな音があります。いろんな音色を味わうように、自分の中に湧き起こるいろんな感情も味わえたなら、どんなに素敵でしょう。ちょっと気の遠くなる境地ですが。
いつも私にインスパイアを与えてくださるイリーナさんのピアノ。出会えたことに改めて心からの感謝を(ブログペトロフピアノ)。
まずは花を買って
家のこと
2016年09月26日

前回のブログ(ブログ体の声)でもお知らせしましたとおり、9月から定休日を毎週水曜日と第二木曜日に加え、第四木曜日も休ませていただくこととしました。
これまで連休といえば月に一度。開店からしばらくは、あれこれ用事をこなしている間に気づけば終わり。なんていうことの繰り返し。これでは味気ないと、思いついたのが花を買うことでした(ブログ私が苦手だったもの花)。
連休初日の水曜の朝、まずは自宅近くのフィットネススタジオへ。その帰り道、買い物に立ち寄るスーパーマーケットで、併設の花屋さんに立ち寄ってみることに。
思うままに選び、思うままに活けた花は、その時の私そのものに思えました。 今日、明日は「しののめ寺町」月に一度の連休。まずは花を買って。 ふと、こんなフレーズが浮かびました。
写真におさめ、その時の思いを綴ってフェイスブックに投稿してみました。フェイスブックをご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。ネット上で公開できる短い日記のようなものでしょうか。基本的に匿名性がなく、許可した交友関係のみ閲覧できるのが便利なところです。 たとえば、こんな感じ…。 
今日、明日は「しののめ寺町」月に一度の連休。まずは花を買って。 なんだか慌ただしい毎日。 自信があっても、なくても…。 なくても、なくても…。 前に進んでいかなくちゃ。 がんばれ、あさっての私。 2015年8月12日

今日、明日は「しののめ寺町」月に一度の連休。まずは花を買って。 「変える」って大変! 頭をいっぱい打った一週間。学びの時間だったかな。やらなきゃよかった、では終わらせたくない。より良いものに変えていくために、しなやかでタフな心にならなくちゃ。 2015年10月7日

今日、明日は「しののめ寺町」月に一度の連休。まずは花を買って。 新体制でスタートした新年。緊張して過ごした一週間。 不安は希望を孕(はら)んでいる…。 どこからやってきたのか、そんな言葉がしきりに浮かんだ一週間でもあり。 2016年1月13日
以来、連休に花を買い、写真に撮り、フェイスブックに投稿する。そんな作業が、月に一度の習慣になりました。
花の写真は思いのほか難しく、ましてや古いデジカメ、腕はなし。ああでもないこうでもないと、何度も撮り直しては編集し…。貴重な休みになにをやっているんだか、と呆れながらも、なんだか楽しい時間です。
なんとか納得の一枚を選び、ありのままの思いを添えて投稿を終えると、胸のすくような解放感。期せずして、一ヶ月にたまった思いを整理し、放出するいい機会になっていたようです。
かれこれ2年半ほど続けたでしょうか。今月から連休が月に二度になるのに合わせ、ひとまず終わりにすることに。改めて過去のフェイスブックをさかのぼって見てみました。
一枚一枚の花の写真、それぞれに添えられた言葉。それは「しののめ寺町」と共に歩いてきた私の思い出のアルバムのよう。
今日、明日は「しののめ寺町」月に一度の連休。まずは花を買って。 私の中ですっかりお馴染みになったフレーズ。一ヶ月がんばった自分をねぎらってくれた、お気に入りの言葉でした。
唱えるだけで、そのときどきの思いが鮮明に蘇り、今でも胸が熱くなります。 この言葉からも卒業。これからは月に一度と言わず、気が向いた時に花を買い、いつでもいつでも自分の思いを大切にできる私でありたいと願っています。
さっそくですが、9月21日(水)22日(木・祝)が連休となります。お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが、元気で店を続けていけるよう、いただいたお休みを有効に過ごしていきたいと思っております。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
体の声
心と体のこと
2016年08月27日

ご挨拶が遅くなりましたが、8月17日から21日まで5日間の夏休みをいただきました。ありがとうございます。皆様はどんな夏を過ごされたでしょうか?
私は仕事でもプライベートでも、なにかと考えなければいけないことが多い夏でした。そうしたひとつひとつに、決断や選択をしていかなければいけないところなのですが…。
どうしたことか、私の中のいろんな私が口々に好きなことを言って、頭の中がやたらやかましい状況。いちいち聞いていたらきりがなく、決断を先延ばししたり、選択が二転三転したり。 果ては「カリスマリーダー、早く出てきてぇ~」と叫んだり(笑)。自分でも不思議なくらい優柔不断な状況に陥っていました。
そんな私に、こんなアドバイスをくださる方が。いつも、そのときどきに適切な言葉をかけてくださる人生の大先輩です。
「頭の声より、体の声を聞いてあげてはどうでしょう」
以前にも伺っていた言葉ですが、これが結構、難しい。頭の声はにぎやかで、体の声は控えめ。体の声は頭の声にいつもかき消されてしまいます。
「体は我慢強いのでなかなか弱音を言いません。こちらから聞いてあげないと。頭は嘘をつきますが、体は正直です」とも。
ちょっとショッキングな言葉ですが、確かにそうです。頭の声はまことしやかなことを言います。こうあるべき、とか。これくらいできなくてどうする、とか。その根拠はというと、案外いい加減だったりして。
頭の声に引っ張られて行動していると、いつか無理が生じる気がします。気づけば体はくたくた。体の声はまさしく身をもって語られる言葉。嘘、偽りなく訴えてきます。
昨年、夏休みに入った途端、ダウンしてしまうという苦い経験をしました(ブログユルスナールの靴2)。夏休みに入る直前、決して昨年の二の舞をすまいと、用心深く体に注意を払うよう心がけてみることに。
すると、ずいぶん早い時間から眠たくてしょうがない自分に気づきました。早々にベッドに入ると、たちまち深い眠りに就き、翌朝の体がとても楽。もしかして、本当はいつも眠たかったのかも。なんて思う私に、どこからか「うん」という微かな声が聞こえたような。
たまたまだったのかもしれませんが、私にはとても暗示的な出来事に思えました。自分の体と交信したような感覚。気に掛けられることで、体は安心し、素直な反応を返してくれたのだと思います。お陰様で昨年とはうって変わり、元気な夏休みを過ごすことが出来ました。
体の声は、単に体の好不調だけなく、さまざまなメッセージを送ってくれるような気がします。よりよく生きていくための大きなヒントが含まれているような。まだよくわかりませんが、そんな気がしてなりません。
上の写真は、週に一度通っているアロマキャンドルヨガのスタジオ風景です。ここに来るとたちまちリラックスして、毎回、あくび連発の私。まさに体と向き合い、体の声を聞く貴重な時間となっています(ブログ体)。
日々の暮らしのなかで、体に語りかける時間を増やしていきたい。そうして、体の声を聞き分け、体からのメッセージをキャッチし、よりよく生きていきたい。そんなことを思っています。
まだまだ懸案事項は山積みですが、そんななか答えを出せたことがひとつ。定休日の追加です。9月から現在の定休日、毎週水曜日と第2木曜日に加え、第4木曜日も休ませていただくこととしました。ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解の程よろしくお願いします。
最後は業務連絡のようになってしまいました(笑)。元気に過ごせたことに感謝しつつ、後半戦もまたがんばっていこうと思う夏の終わりです。