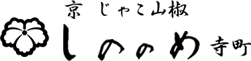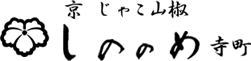ベニシアさんのこと
素敵な女性
2019年09月22日

先日、素敵な展覧会に出かけてきました。「ベニシアさんの手づくり暮らし展」です。
ベニシア・スタンリー・スミスさんという女性をご存じでしょうか? ご実家は本物のお城という、イギリス貴族の家系のお生まれ。けれど19歳で貴族社会を離れ、インド滞在を経て日本へ。やがて京都大原の地にたどり着かれます。
大原というのは京都の北の方。市内中心部からみると、とてものどかな地域です。そんな自然の中に建つ築100年の古民家を買い取り、日本人のご主人と共に自分たちで手直しをして住まわれるように。
ハーブを中心に、食や手仕事、周囲の方たちとの交流を大切に、それはそれは素敵な暮らしをされているご様子は、NHKの「猫のしっぽ カエルの手」でお馴染みで、私もその番組を見てべニシアさんを知った次第です。
会場では実物を使って、ご自宅のキッチンやお庭が再現されています。一つ一つ選び抜かれた調度品は、やはり貴族の生まれという環境の中で育まれた審美眼によるものなのでしょう。えもいわれぬ存在感のあるものばかりです。
広大なお庭は、エリアごとにストーリーをもって作られ、まるで絵本に出てくるおとぎの国のよう。
日本人が忘れてしまっているような日本の伝統的なものと、ヨーロッパの香り漂うものとをうまく融合させ、オリジナルの世界観が広がるお住まい。そしてライフスタイル…。東洋と西洋がやさしく調和した様は、まさにベニシアさんそのものに思えます。
ひとはそれまでの人生で培ってきたもので出来ているんだなぁ。そう思わずにはいられません。
会場ではご主人である山岳写真家、梶山 正さんによる写真も多数展示されていました。大原の美しい自然と、それを慈しむようなベニシアさんの表情を捉えた写真の数々。そして傍らに添えられたベニシアさんの詩的なメッセージ…。
自然の移ろいに心を寄せ、敬虔な思いと感謝の気持ちで暮らしておられることが、シンプルな言葉から伝わってきます。なかでも心に響いた一文を書き出してみます。
秋は実りの季節。木の葉が落ちて枯れていくと、
人生について考えてしまいます。
私たちは、日々の悩みや心配事で頭がいっぱいになり、
身の周りの自然の美しさに気づかないことがよくあります。
真っ青な空に浮かぶ傘のような雲や、
秋の可憐なコスモスの上を軽やかに舞う二匹の蝶。
こんな何気ない美しさを、私たちは見逃してしまいがちです。
太陽は毎日、みんなのために輝き、
驚くほど美しい日の出と夕映えを見せてくれます。
なのに私たちは、果てしない考え事で
太陽を雲のように覆ってしまいます。
せめて時々は考えることを止めて、思い出しましょう。
人生は舞台稽古ではなく、美しく生きる機会なのだと。
なんか泣きそうになってしまった私…。
自然に寄り添うことは、自分の心に寄り添うことなんだなぁ。毎日が舞台稽古のような暮らしの中で、いつの間にかパサついてしまっていた心に、慈雨がしみ込んでいくようでした。
数奇な運命に翻弄されることもあったかとお察しするベニシアさんの人生。紆余曲折ありながらも、その時々にご自分の心に正直であられたからこそ、唯一無二な、こんな素敵な暮しにたどり着かれたのだと思います。
展覧会で買い求めた画集は、ベニシアさんのこんなメッセージで締めくくられています。
日本の女性はとても賢い。
疲れていても、悲しくても、いつも微笑み、笑っているから。
私は、日本の女性から「和」と「柔」という英知を学びました。
子供の頃は、人生の意味についてよく考えました。
どうして私たちは生きているのか。
ある日、その答えに気づきました。「幸せになるため」だと。
物事をどう見るかで、幸せは決まります。
知恵と優しさと笑いの心を持って、人生を受け入れましょう。
この境地に至るにはまだまだです。それでも、べニシアさんのメッセージの一つにあるように、日に一度でも空を見上げる時間を持ちながら、自分の幸せを見失わないように生きていきたいものだと思います。
Listen to your heart
自分の心の声に耳を傾けて
たくさんのヒントを与えていただいた展覧会でした。
My Favorite Things
アートなこと
2019年08月23日

このところのブログ、歌のタイトルが続きます。今回はジャズの名曲「My Favorite Things ~私のお気に入り~」です。先日、知人のジャズライブで初めて聴き、たちまち気に入ってしまいました。
知人というのは店を始めてから知り合ったmikiyoさん。彼女のライブについては、このブログでも何度か書いています(ブログ明日に架ける橋 ブログムーンリバー)。
アマチュアながら、魂のこもった歌声が素晴らしく、ジャズに詳しくない私もたちまちファンになってしまった次第です。
これまで3回ほど出かけたでしょうか。毎回、どの曲も素晴らしいのですが、なかでもその日のライブの中でひときわ心惹かれる曲に出会います。「今日の私の一曲!」とでもいうような。
自分では意識していない内奥の気持ちを言い当てられるみたいな、不思議な感覚に陥る曲…。予言めいていたり、神様からの啓示に思えたり。まるで「私のために歌ってくれているの?」と思ってしまうほどです。
それが自分でもおもしろく、今回はどんな「今日の私の一曲!」に出会えるのだろうかと、楽しみに思いながら出かけて行きました。
このライブの醍醐味の一つが、mikiyoさん自身による曲紹介です。英語の歌詞を聞き分けられるわけもなく、前もって和訳を聞けるのは、まずもってありがたいことです。そこに彼女なりの解釈や好みが加わり、曲に彼女の息吹が込められるよう。
一曲一曲の紹介を聞いていると、まるで人生みたいだと思うことがあります。時を超え、国を超え、性別を超え、喜怒哀楽、さまざまな心の機微を味わいながら、あぁ、これがジャズというものなのかなぁ。なんて、生意気にもジャズの片鱗に触れた気分になったりして…。
そんな思いに浸る中盤過ぎ、紹介されたのが「Mornin`」でした。朝の「Morhing」とは似て非なる「呻(うめ)く」という意味だとか。その昔の黒人の方たちの救いのない思いを歌われたもののようです。
朝が来るたび 俺は呻き声をあげる
俺に降りかかってくる あらゆる災難がそうさせるのさ
俺にとっては 人生なんて 負けが決まっている賭けのようなものさ
……
実のところ、その時期、少しばかり不調に陥っていた私。重いリズムが心に迫ります。けれど、奥底に力強い生命力が宿っているようにも思える曲。難しい曲にチャレンジされたmikiyoさんに、心で拍手喝采です。
選曲と共に、曲の順番にもmikiyoさんなりの配慮があるのでしょう。「Mornin`」のあとには「Smile」。チャップリンの「モダンタイムズ」で有名な曲を披露されました。
笑ってごらん 心が傷んでいても
笑ってごらん 心が折れてしまっていても
あの空に雲があれば 君はきっと生きていける
……
前向きな言葉が、暗く沈んだ心に光明を照らしてくれるよう。少し救われた気持ちになります。
そして最後の一曲が「MY Favorite Things ~私のお気に入り~」でした。
バラに滴る雨の滴 子猫のひげ
ぴかぴかの銅のやかん あったかいウールの手袋
ひもで結わえられた茶色の紙包み
みんなささやかな私のお気に入り
……
犬に噛まれた時
蜂に刺された時
悲しい気分になった時
私のお気に入りたちを ただ思い出すの
それだけで気分が良くなるわ
どうしてもうまくいかない時ってあるものです。手に入れたくても入れられないものも山ほどあります。でも、こうしたささかなお気に入りがあれば、人生それでOKさ! って感じでしょうか。可愛らしい歌詞と軽快なノリが楽しい曲です。
ささやかなお気に入りをたくさん見つけること。ないものねだりじゃなく、自分のまわりに既にある素敵なものに気づくこと。それが幸せの近道なんだよ、と教えてくれているよう。
これくらいのものなら、私のまわりにもたくさんありそう。これなら私にもできそう。素敵なヒントを与えてくれた「My Favorite Things」。「今日の私の一曲!」に決定です。
今年は少し長い夏休みをいただきました。ビッグなバカンスはありませんが、映画を観たり、友達と会ったり。気になっていた用事を片づけたり…。普段なかなかできないことをしながら、穏やかな日常を過ごすことができました。
そんな一つ一つがとても愛おしく、幸せに思えた時間。まさに「My Favorite Things」に囲まれた毎日でした。慌ただしい時間の中では見失いがちなことかもしれません。長い休みをいただけたことに心より感謝申し上げます。
大変ご迷惑をお掛けしましたが、お蔭様で心身ともにリフレッシュすることができました。またがんばってまいります。これからもよろしくお願い申し上げます。
時代
アートなこと
2019年07月25日
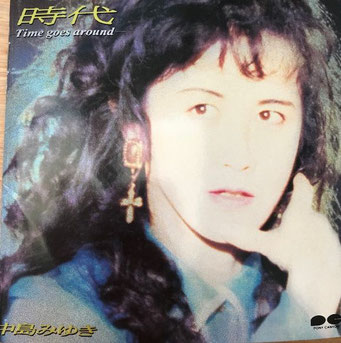
前回の中島みゆきさんの「誕生」について書いたブログ(ブログ誕生)は、思いが溢れ過ぎて、うまく書き切れたか不安な内容でした。が、思いのほか多くの方に「いいね!」をいただき、驚きました。ありがとうございます。
それに調子づいて、というわけではないのですが、今回も引き続き中島みゆきさんの歌について…。
皆さんはご自分の応援歌っておありでしょうか? 世代によって実に様々なことと思います。
戦後、美空ひばりさんの歌に励まされたという話はよく聞きます。フォーク、ニューミュージック…。今の時代なら誰のどんな歌でしょう? もう私にはついていけないかも(笑)。
かくいう私は、やっぱり中島みゆきさん! 「時代」です。
今はこんなに悲しくて 涙も枯れ果てて
もう二度と笑顔にはなれそうもないけど
そんな時代もあったねと
いつか話せる日が来るわ
あんな時代もあったねと
きっと笑って話せるわ
だから今日はくよくよしないで
今日の風に吹かれましょう
ポピュラーコンテスト、通称ポプコンで優勝され、彗星のごとく世に出てきた歌と記憶します。なんて書くと、世代がわかりますね(笑)。
デビュー曲と思っていましたが、改めて調べてみると「アザミ譲のララバイ」に続くセカンド・シングルなのだとか。意外でした。
初めて聴いた時、「そういうことって、あるある!」って思わず手を打ってしまったような。シンプルな歌詞が心にストレートに響いたのを覚えています。
学生から、就職、結婚、育児。その後のあれこれ…。その折々に口ずさみ、気づけば私の応援歌となっていました。
やはり辛い時に口ずさみたくなる歌ですね。「そんな日がホンマに来るんかいな!」なんて思いつつ、時に泣きながら歌うこともあったかな。
そんな励まし続けてくれた応援歌も、口ずさめなくなる時期がありました。
まわるまわるよ時代は回る
喜び悲しみ繰り返し
今日は別れた恋人たちも
生まれ変わってめぐり逢うよ
この部分が、どうしても腑に落ちなくなってしまったのです。時代なんて回らない。ずっと平坦な荒野が続くばかりじゃないか。この歌詞は間違っている、と…。
天才的アーティストの名曲に異を唱えるなんて失礼千万なことですが、その時の正直な思いでした。
そんな時期が何年続いたでしょう。また時が過ぎ…。思いもよらないことに、家族で商売を始めることになりました。果てしなく続くと思っていた荒野が、突然のどんでん返しです。
店を始めてからは、毎日が喜びと悲しみの繰り返し。目が回るくらい(笑)。気付かない間にも、時代は回っていたんですね。あぁ「時代」の歌詞は間違っていなかったと、中島みゆきさんに心で詫びて、再び私の応援歌に復活と相成りました。
旅を続ける人々は
いつか故郷に出逢う日を
たとえ今夜は倒れても
きっと信じてドアを出る
たとえ今日は果てしもなく
冷たい雨が降っていても
辛い歌詞なのに、なんて希望に満ちているんでしょう。人間の底力を信じずにはいられない気持ちになります。
まわるまわるよ時代は回る
別れと出逢いを繰り返し
今日は倒れた旅人たちも
生まれ変わって歩き出すよ
豊かで平和だけれど、一方で生き辛いことも多い時代。「そんな日がホンマに来るんかいな ?!」と、やっぱりツッコみたい気持ちになることも。
それでも、口ずさんでみると、そんな気がしないでもないと思えてくるような。長く歌い継がれてきた歌には意味があるのだなぁと思います。
名曲は、長きにわたり、そのひとの人生に寄り添ってくれるものですね。「時代」は私にとって、まさにそういう歌です。いくつになっても口ずさんでいきたい。そう、しきりに思うこのごろです。
誕生
アートなこと
2019年06月20日
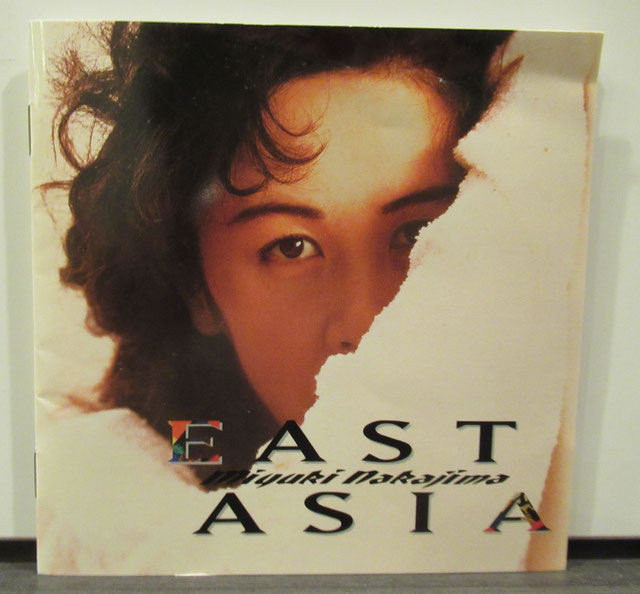
中島みゆきさんの「誕生」という歌をご存知でしょうか? このところ私のもっぱらの愛唱歌となっています。
ひとりでも私は生きられるけど
でもだれかとならば 人生ははるかに違う
こんな歌詞で始まる歌。切ない恋の歌かと思いきや、後半、壮大な愛の世界にぐいぐいと導かれていきます。
めぐり来る季節をかぞえながら
めぐり逢う命をかぞえながら
畏れながら憎みながら
いつか愛を知ってゆく
泣きながら生まれる子供のように
もいちど生きるため 泣いて来たのね
初めて聴いた時、鳥肌が立つ思いがしました。なんてスケールの大きな歌かと。今でも聴くたびに心揺さぶられますが、なかでも印象的なのが、この部分…。
Remember 生まれた時
だれでも言われた筈
耳をすまして思い出して
最初に聞いた Welcome
Remember 生まれたこと
Remember 出逢ったこと
Remember 一緒に生きてたこと
そして覚えていること
赤ちゃんの誕生は祝福に包まれているものです。こうして生まれた命。今、どんな困難を抱えていたとしても、ひとは皆、生きていく価値があるんだよ。私も、あなたも、誰でも…。
そう語りかけてくれているようで、自信を失い落ち込む時。あるいは、まわりにそういう人を見る時。エールを送るように、思わず心の中で口ずさんでしまいます。
こんな言葉を世に送り出せる中島みゆきさんという人。あぁ、天才的なアーティストだなぁと感心するばかりです。
話は変わりますが、テレビをつければ、毎日、悲惨なニュースが飛び込んできます。なかでも立て続く幼児虐待のニュースは、やり切れない思いがします。
いたいけな体と心に受けた傷はいかばかりか。短い人生、わずかでも楽しい時間はあったんだろうか。いっそ生まれてこない方が幸せだったんじゃないだろうか。
そんな思いに駆られる時、心に浮かぶのが「誕生」最後の絶唱部分です。
Remember けれどもしも思い出せないなら
私 いつでも あなたに言う
生まれてくれて Welcome
確かに、望まれないで生まれてきた命があるかもしれない。でも神様は祝福してくれたよ。生まれてこない方がよかった命なんて一つもないんだよ。
力強い歌声は、絶望のなかで亡くなっていった幼子の魂にそう語りかけているようで、一片の救いがもたらされる気がします。
それは、そうした幼子だけでなく、あまねく私たちへも語りかけられているのかもしれません。
祝福されて生まれてきたはずなのに、日々の困難さから、忘れてしまっている人。自分なんてなんの価値もないと自暴自棄になってしまっている人。そうした人がたくさんいる時代のように思えます。
「誕生」は生き辛い今の時代に贈られた、天上からのメッセージのよう。
縁あって、この世に誕生した命。生まれて、出逢って、生きていく命。誰もが個々の命を慈しみ、全うできたらいいな。
「誕生」の歌を口ずさみながら、そんなことを切に願うこのごろです。
堀文子さんの言葉4
素敵な女性
2019年05月13日

私が敬愛する女性の一人、堀文子さんが今年2月、100歳でお亡くなりになりました。「群れない」「慣れない」「頼らない」をモットーに、絶えず新たな画風を切り拓いてこられた孤高の画家です。
訃報は残念ではありましたが、天寿を全うされたというにふさわしい見事な人生。お疲れ様でしたとご冥福をお祈りするばかりでした。
そんな折、京都高島屋で堀文子展が催されるというニュースが届きました。生誕100年展が、巡回中に追悼展になったとのこと。これもまた見事な巡り合わせに思えます。
堀文子さんを知ったのは、ずいぶん前に放送された教育テレビ「日曜美術館」でのことです。ご本人が、自身の創作活動をそれはそれは楽しそうに話されるのが印象的でした。司会の壇ふみさんがまぶしそうに向けられていた視線が、私の視線そのもののように感じたのを覚えています。(ブログ画家 堀文子さんのこと)
それからだいぶ経った数年前、とあるブックカフェで偶然に堀文子さんのエッセーに出会いました。楽し気に創作活動を語られていた、その笑顔の向こうにある孤独と厳しさ…。以来、心から敬愛するようになりました。(ブログ堀文子さんの言葉3)
とはいえ作品を観るのは、テレビや著書のなかの写真でばかりでした。今回、初期の作品から絶筆まで一堂に会されるとのこと。矢も盾もたまらず出かけて行きました。
会場はテーマに沿ってコーナーが設けられていました。角を曲がるごとに現れる新しい画風の絵に、驚きと感動の連続。その多彩さは、いったい何人の画家の手によるものかと思うくらいです。
なかでも今回、一番楽しみにしていた作品があります。「幻の花 ブルーポピー」。標高5000メートルのヒマラヤに、この世ならぬような青色の花が咲くと知り、82歳でヘリコプターに乗り、酸素マスクをつけ、岩場を上り下りし、命がけで探し当て、スケッチされたという花の絵です。
会場後半でいよいよ対面できた「幻の花 ブルーポピー」。花は可憐だけれど、外敵から身を守るためなのでしょう、根元にはこれでもかというほどの鋭利な棘。その絶対的な存在感に驚かされました。
過酷な環境で、誰の目に留まることなく、ましてや褒められることもない。それなのに、一体なんのためにと思うほど美しく、逞しく咲く花。気高いその姿は、まさに堀文子さんが愛された「孤高」を体現したかのようです。
やっと出逢えた憧れの絵でしたが、うれしさよりも戸惑いの方が大きかったかもしれません。心地良い美しさとは全く違う、痛みを伴う美しさ、とでもいうのでしょうか。それは生まれて初めての感覚。出逢ったことのない「美」でした。
「美」は私が思っているより、もっと多様なものなのかもしれない。
「花の画家」とも称される堀文子さん。最晩年のコーナーに向かうと、描かれる花や木々も、終焉をイメージさせるものが増えていきます。
けれど決して寂しげでも、はかなげでもありません。虫食いだらけだけれど、フィナーレを飾るにふさわしい鮮やかな色彩の落葉。凄みすら感じられる、枯れ果てたひまわりの立ち姿。絶筆の紅梅の赤は、私には命ほとばしる鮮血の色に見えました。
「美」は生き様そのものなんだなぁ。
知人で洋画家の野見山暁治さんが、こんな追悼文を寄せておられます。堀文子さんはよくお酒を召し上がる方だったそうですが、酔うと「あたしはね、今まで流した涙の量だけ飲むのよ」と漏らされることがあったとか。そして、自分で言ってきまり悪くなると、少しばかり不機嫌になったりされると。(京都新聞 2月21日掲載)
孤独の空間と 時間は 何よりの 糧である。
堀文子さんの言葉です。この言葉の向こうに、どんな人生があったんだろう。人知れず、どれだけの涙を流してこられたんだろう。想像も及びませんが、堀文子さんの人間臭い一面を垣間見させてもらった気がするエピソードです。
「なんで、そんなことをばらすのよ!」と、天上で苦笑いしておられる堀文子さんのお顔が浮かぶようです(笑)。
追悼文はこう結ばれています。あれだけ日本画で新しい世界をつくり、多くの人を魅了しながら、ついに国からは何の栄誉も与えられなかったことを、ぼくは堀さんの素晴らしい勲章だと思っている、と。
自由で革新的なグループを活動の場とし、最後はどこにも属することなく、全く自由な創作に徹せられたとのこと。勲章を与えられなかったことは意外で、あれこれ憶測をしてしまいます。が、堀文子さんの前では、そんなこともつまらぬことに思えてきます。まさに「幻の花 ブルーポピー」の如し。
私もいつか「幻の花 ブルーポピー」としっかり向き合えるようになりたい…。
堀文子さんから宿題をいただいたような気がする展覧会でした。ご冥福を心よりお祈り申し上げます。