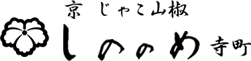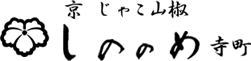じゃこ 桜
店のこと
2016年04月08日

もう召し上がってくださったお客様もいらっしゃるでしょうか。「しののめ寺町」の新商品「じゃこ 桜」。ほのかに桜の香りのするおじゃこです。
「山椒メレンゲ」を作ってくださっている洋菓子店「シェ・ラ・メール」さんには、日頃よりなにかとお世話になっています。店のこと、商品のこと、いろいろアドバイスをいただくことも多いのですが、そんななか出てきたのが、おじゃこに桜の葉の塩漬けを混ぜてみたら? というアイデア。
さっそく材料の手配までしてくださり試作してみると、ちりめんじゃこと桜の相性のいいこと! 新商品を作ることは、かねてよりの念願ながら、なかなか実現できずにいたのが、あれよあれよという間に完成。名前はシンプルに「じゃこ 桜」と決めました。
桜の便りが待たれる3月の第2土曜日、販売を開始するや、たちまち「じゃこ 桜、ください」と店に入ってこられるお客様が次々と。店頭に置いた黒板のチョークの文字「新商品 春限定 じゃこ 桜」をご覧になっての模様。これまで黒板の効果など実感したことがなかったので、とても驚きました。
お味見いただくと「ほんと、桜の香り」「おいしい」と口々に仰ってくださり、早い時間に売り切れることも。毎日お客様と間近に接している私ですが、今回の反応はいつになく新鮮でした。
ご挨拶が遅れましたが、3月16日で「しののめ寺町」は開店から四周年を迎えました。ひとえにご愛顧くださっている皆様のお蔭、心から感謝申し上げます。今年は特に企画を考えていなかったのですが、偶然「じゃこ 桜」誕生と同時期に。ご好評いただけたことが、なによりの励みとなりました。
ひと口に開店といっても、まったくの一から始める場合と、既にある店から独立して始める場合があります。うちは後者です。どちらも大変なことですが、独立の場合、一番大変なこと。それは常に比較されることが宿命づけられていることではないでしょうか。それも並列の比較ではなく。
殊に味に関しては「同じ」であることを強く求められます。今でも「同じ味ですか?」と確認されることがよくあります。その都度、同じ業者さんから仕入れ、同じように炊いている旨お伝えしていますが、ご納得くださるお客様もあれば、不安を残されたままのお客様も。いつも胸痛むところです。
実のところ、ちりめんじゃこが自然のものなら、作る人間も生身の体。「同じ味」に仕上がることを目指しつつも、まったく同じ味など有り得ないことは、以前のブログで書いた通りです(ブログ味)。
さらに、正直に書くことをお許しいただけるなら…。
味だけでなく、なににおいても、自分たちは自分たちなりの「よりよいもの」を目指して、日々邁進しているつもりです。そうした自分たちの仕事が、他のどこかにある基準を元に評価されることが、時に辛いなぁと感じることがあります。仕方ないこととわかっていながらも。
正直に書き過ぎています。申し訳ありません。
新商品「じゃこ 桜」が誕生し、なによりうれしかったこと。それは、そのものが評価される心地よさでした。たとえよくない評価であったとしても、他のなにかとの比較ではなく、ストレートにそのものが評価される潔さ。それは今までに経験したことのない感覚でした。
生まれたばかりの未熟な「じゃこ 桜」ですが、「オリジナル」とはこういうことなのだと教えてくれたように思います。
なにを踏襲し、なにを変えていくのか。独立した店の大きな課題です。踏襲していくだけでは限界があります。が、「変える」ということには、どこか罪悪感がつきまとい、大きなエネルギーを要します。いつも葛藤の四年間でした。
守るべきものは守りつつも、自分たちの感性で独自の店を築いていきたい。自由に、しなやかに…。今回、そう強く思いました。
「じゃこ 桜」が四周年に合わせて誕生したのは、決して偶然ではなかったのだと、今では思っています。きっかけを作ってくださった「シェ・ラ・メール」さんには感謝の思いでいっぱいです。
来年の五周年に向け、またがんばっていく所存です。今後ともますますのご愛顧、応援のほどよろしくお願いします。
働きたい!
店のこと
2016年03月16日

気付いていただいているお客様もいらっしゃるでしょうか? 昨年10月からの大学生のアルバイトさん、さなさんに続き(ブログおぉきに)、今年1月から若いママさん3人が日替わりで来てくださっています。
店頭やホームページで募集するもなかなか見つからないなか、常々素敵だなと思っていたお客様に紹介をお願いしたところ、思いがけずもご自身が来てくださることに。しかもお友達を誘って。願ってもないことでした。
まだ幼稚園児がおられるママさんたち、来ていただける時間は限られます。それでも働きたいという思いをお持ちとのこと。どんな条件より、その思いが一番大事なんじゃないかと、お願いすることにしました。
幼稚園の行事や、子供さんの病気の時などは、ママさんチームで代わり合って。うちも忙しい時、のんびりの時と様々。お互いに相談しながら臨機応変にやってていきましょうという、ゆるい感じでのスタート。明るく素敵な皆さん、仕事のみならず、私の精神的支えにもなっていただいています。
結婚を機に、勤めていた会社を当たり前のように退職した私。当時は一般的なことでした。間もなく出産、育児の始まり。子どもが成長してからも、自分が置かれた状況を考え合わせ、家庭人として暮らしていくのがいいと思っていましたし、自分になにか出来るとも思っていませんでした。
そうして選択したのが「ほぼ専業主婦」のスタイル。家庭を中心に置きながら、ささやかでいいから、なにかしら自分を表現できること、打ちこめることを見つけたい。あれこれ模索し、手を出しましたが、結局どれも中途半端。いつも不完全燃焼な自分を持て余していたように思います。
思いがけず店を始めることになり、必要に迫られ始まった仕事中心の生活。自由な時間はなくなり、心身とも休まらない毎日に。それでも「ほぼ専業主婦」だった頃を懐かしく思うことはあっても、戻りたいと思うことはありません。忙しく働いている今がいい。
私は働きたかったんやなぁ。
今思うと、自分の置かれた環境や、自分の能力に、私自身が枠をはめていたのではなかったか。自分で自分を不自由にしていたような。
どうしたって制約のある女性のライフスタイル。そのなかでも、持てる力をいかんなく発揮し、自分らしく働ける場があるといいなと思います。主婦能力はとても優れたものだと、私は思っています。本人自身が気づかないまま、まわりからも評価されないまま埋もれている能力が、世の中にはいっぱいある気がしてなりません。もったいない!
子育て中のママも、介護中の男性も、若者もシニアも、ハンディキャップを持った人も、働きたいと思うひと誰もが、その人らしく働ける世の中であればいいな。職業に貴賤などなく、誰もが正当に評価される世の中であってほしい。
大学生のさなさんは、春から地元に帰って就職とのこと。大きな助けになってくれた彼女、残念ではありますが、お別れです。
アルバイトさんの歓送迎会を催すこと。それは「しののめ寺町」開店以来の夢でした。写真はまさにその夢が叶った時のもの。夢に描いていた以上に素敵な会となりました。
新たに縁あって一緒に働くことになった方たち、ゆきさん、めぐみさん、まりさんです。仕事ではありますが、どうせなら楽しい時間を共有していきたいと思っています。皆様もどうぞよろしくお願いします。
なお、さなさん卒業に伴い、土日に入っていただける方を急募しています。私たちのお仲間になってくださる方、ぜひご一報ください。
こちら側の笑顔
店のこと
2016年02月29日

最近、私の中でテーマとなっている言葉があります。昨年末、ある会で聞いて以来、気になって仕方ない言葉です。
「こちら側の笑顔」
少し以前に、中小企業家同友会に入会したことを、このブログでも紹介しました(ブログ中小企業家同友会)。会員同士が経営について真摯に学び合う会で、時間が許す範囲で、例会に参加させていただいています。
その日は宮崎にある着ぐるみを制作する会社「KIGURUMI.BIZ(株)」の取締役工場長さんを報告者に招いての例会でしたwww.kigurumi.biz。私と同年代と思われる女性。終始にこやかな表情がとても素敵です。柔らかな口調で語られる、厳しくも楽しい会社経営のお話に、たちまち引き込まれていきました。
そんななか出てきたのが、「こちら側の笑顔」と「向こう側の笑顔」を叶えるために…というお話。
「向こう側の笑顔」はお客様の笑顔です。お客様の笑顔を見ることは、商売をする者にとってなによりの喜び。そのためには、いくらでもがんばれるものです。ただ、そこにばかり目が行くと、無理が生じ、疲れ果て、結果、お客様に喜んでいただけるいい仕事ができない、ということも。
そこで大切なのが「こちら側の笑顔」。働く側の笑顔です。働く人間が、まず笑顔でいられることが大切だと気付かれてからの大改革。その経緯を話されたのですが、社員全員が女性というこの会社。挙げられる例えも、私にはわかりやすく、なるほどと感心させられることばかりでした。
ビデオやパンフレットで紹介される社員さんは皆、本当に素敵な笑顔。その手で作られていく着ぐるみたちも、とっても幸せそう。受け取られるお客様の笑顔が目に浮かびます。実践の成果が一目瞭然。
「しののめ寺町」は、間もなく開店から4年を迎えようとしています。多くのお客様に来ていただくには、どうしたらいいのか。来てくださったお客様に喜んでいただくには、どうしたらいいのか。そんなことを考え続けてきた毎日だったように思います。今なお…。
店と自宅を往復。店をやっている人間であり、家庭を切り盛りする人間であり。ひとりの人間であり、ひとりの女性であり…。一日24時間、体は一つ。慣れないうえに要領の悪い私。やるべきことを優先順位の一位から当てはめていくと、とてもじゃないけど収まらない。
上位はどうしたって店のこと。下位はやっぱり自分のこと。結局いつも泣く泣く切り捨て。なんてことの繰り返し。それでもお客様の笑顔が見たいという思いが力強い原動力となって、私を突き動かしてきてくれたように思います。
でもやっぱり、4年の間には、どうしても笑顔になれない日もあったかなぁ。正直に言えば、涙を拭き拭き店に立った日も、一日二日はあったかなぁ。プロじゃないなぁ。今さらながら反省しきりです。
よくかけられる言葉があります。店に立つ人間が輝いていないと、その店は輝かない。店に立つ人間が幸せじゃないと、その店は幸せになれない。あなたが輝いていること。幸せでいること。それが大事、だと。
どんな仕事もそうでしょうが、商売もやはり厳しいものです。課題山積、日々、切磋琢磨していなければ続けていくことはできません。といって必死の形相をしていたのでは、お客様も逃げていかれるでしょう。
まずは私が心身ともに健康で、人として幸せを感じられる毎日を送っていること。それこそが商売をやっていくうえで、一番基本となることなんじゃないか。そう思うようになりました。
考えれば、「向こう側の笑顔」はお客様ばかりではありません。家族だったり、さまざまなひと付き合いだったり、いろんな「向こう側」に囲まれ暮らしているものです。そこでもついつい「向こう側の笑顔」を窺うあまり「こちら側の笑顔」を忘れがち、なんてことも。
「こちら側の笑顔、こちら側の笑顔」と心で唱えると、人差し指に乗せたやじろべえが振れて、うまくバランスをとってくれるよう。私の魔法の言葉となりました。
この言葉との出会いに導いてくださった、たくさんのご縁に感謝しながら、春を待つこのごろ。改めまして、今後ともよろしくお願い申し上げます。
佐藤初女さんのこと3
素敵な女性
2016年02月16日

哀しい訃報が届きました。このブログでも何度かご紹介している佐藤初女さんが、2月1日、94歳でお亡くなりになりました。(ブログ佐藤初女さんのこと ブログ佐藤初女さんのこと2)
なにかのきっかけで初女さんのことを知り、本を読んだり、講演に出かけたり。そうするうちに初女さんの作られたお料理をいただきたくてたまらなくなり、青森県弘前市の岩木山麓にある「森のイスキア」を訪ねたのが6年近く前のことです。
一度乗ってみたいと思っていた寝台車で、一人、夕刻に京都を出発(ブログさよなら 寝台特急 日本海)。翌早朝、弘前に到着。駅前からバスに揺られ、山の中へ、山の中へ。1時間近く走ったでしょうか。指定のバス停に降り立つと、見渡す限りなにもない平地。ファックスで届いた手書きの地図を片手に、その中の一本道をさらに山の中へ、山の中へ。
6月の始め、青森は梅雨前だったでしょうか。すでに蒸し暑かった京都とうって変わり、暑からず寒からず、とても爽やかな季節でした。広い広い空。青空に白い雲。そんな天気と裏腹に、私の心は曇り空。この道を行けば本当に辿り着けるのか、不安でいっぱいでした。
私、なんで、こんなとこ歩いてるんやろ…。
一体なにに掻き立てられて、こんなところまでやって来たのか。聞こえてくるのは、私がひくキャリーバッグの音ばかり。いつも自分を持て余し、手を焼いているもうひとりの私が、呆れ果ててぶつくさ言いながら、渋々うしろをついてくるようでした(笑)。
どれくらい歩いたでしょう。本や映画で見知っていた「森のイスキア」が目の前に現れた時、桃源郷を見つけたひとは、きっとこんな気持ちだったんだろうと思いました。
スタッフの方に温かく迎え入れられると、NHKテレビの撮影の最中でした。初女さんの代名詞、おむすびの実演を目の当たりにでき、しかも昼食にいただけるという幸運。夢にまで見ていたことが、あっけなく叶っていくことが、また夢のようでした。
その後、宿泊者が次々に到着。初女さんに一目会いたくて、全国から集まってきたひとばかりです。持ち寄ったお土産でお茶タイム。台所で夕食作りを間近に眺め、大きな丸い卓袱台を囲んでの夕食、歓談。まるで田舎に親戚が集まったような懐かしい風景でした。
初女さんは当時すでに88歳だったでしょうか。耳が遠く、離れたひとの声は聞き取りにくいご様子でした。耳の遠い義母に慣れていたせいか、私の声は不思議とよく聞き分けてくださり、「通訳して」と仰ることも。初女さんに身を寄せ耳元でお伝えすると、小さく頷いては、その方に向かって返事をされていました。
とても光栄なお役目を賜ったようで、うれしい思いでした。が、その年齢で朝から夜まで宿泊者の世話をし、皆の話に耳を傾けられることは、想像以上に過酷なことなのではと、胸痛む思いもしました。
最晩年まで、乞われれば全国、海外にまで、講演や講習に出かけておられたようです。訪ねて来る人は、来るもの拒まず、可能な限り迎え入れられていました。人になにかをしてもらおうなどとは微塵も思わず、常に自分が人に出来ることはなにかを考えておられる方でした。そうして出会った一人一人の心の中に、それぞれ一粒の種をまいてこられた人生だったのではないでしょか。
持てる力を使い切り、使命を果たし切り、天に召されたのだと思います。敬虔なクリスチャンだった初女さん。訃報はショックではありましたが、神様のもとに召されてやっと安息につかれたのだと、なにかしらほっとする思いもありました。
冒頭の写真は、朝食の準備をされている初女さんです。お料理は数人のスタッフの方が手伝って作られますが、お米の水加減は初女さんにしかできないとのこと。前日の夕食の準備でも、炊飯前に水に浸したお米をつまみ上げ、ふくらみ具合を見ながら、慎重に水加減を調整しておられた姿が印象的でした。
そうして炊き上がったご飯を、慈しむようにほぐしておられる初女さん。その背中に、窓から朝日が降り注ぎ、神々しいばかりのお姿でした。気づけば、まわりで皆のシャッターを切る音が。失礼かと思いましたが、この瞬間を残しておきたい一心で、私も一枚。
肖像権など問題がないかと心配ですが、皆様にもぜひご覧いただきたく思い、掲載しました。初女さんはきっと、津軽訛りのか細い声で「構いませんよ」と仰ってくださると思います。
私、なんで、こんなとこ歩いてるんやろ…。
あの日、「森のイスキア」に向かう道すがら感じた疑問。その答えがわかりかけている気がしています。私も一粒の種がほしかったのかも…。
初女さんのおむすびをいただく幸運に出会えた一人として、私に何ができるのか問いかけながら、いつか種から芽吹かせ、花開かせる日が来ることを願って、これからも進んでいきたいと思っています。
初女さん、本当にお疲れ様でした。安らかにお休みください。

タンザニアのお友達
心と体のこと
2016年01月31日

店を始めて、さまざまな方と出会う機会に恵まれるようになりました。世の中には多彩な方がいらっしゃるもんだなぁ、と感心することしばしばです。
そういう方たちの考えられること、行動力は、私などからすると型破りに思えて驚くばかり。同時に、驚いている自分がまだまだ小っちゃいんだなぁと気づかされます。
なかでも、最近とりわけ驚いた出来事が…。知人のご家族が、まだ幼い子供さんを連れて、アフリカのタンザニアに引っ越されたのです。日本の支援で、教育機会に恵まれない女子のための学校が開校されたとのこと。ご主人は理科教師として、奥様は文化交流担当として勤められるようです。
特に親しい間柄というわけではないのですが、私が恐る恐る書いたブログ「紅葉の頃 思うこと」(紅葉の頃 思うこと)にご主人が温かいメッセージをくださったのが印象的でした。希少難病患者支援事務局主催のイベントに出店した折に顔を見せてくださったのも嬉しいことでした(ブログ希少難病患者支援事務局SORD(ソルド)、ブログ希少難病支援事務局SORD(ソルド)2)。失礼ながら、私と感性の近い方なんじゃないかと、勝手に親しみを感じていました。
二年近く前になるでしょうか、ご家族で来店くださったことがあります。当時生まれて間もないお子さん、ねねちゃんを「人見知りが始まって」と言いながら、いきなり手渡されました。赤ちゃんを抱くなんて久し振りの私、ぎこちなく抱っこし、いつ大泣きされるかと内心ひやひや。
ところが、ねねちゃん、私を見つめて満面の笑み。私もつられて笑みがこぼれます。その様子を見たパパさん、「ねねが泣かなかったのは、木村さん(私)とタンザニア人の友人だけです」って。えぇ~!! 以来、私のなかでは、私とねねちゃんとタンザニア人はひと続きのものになりました(笑)。
その後もフェイスブックを通じて、ねねちゃんの成長とご家族の睦まじさを、遠い親戚のように楽しませていただいていました。そんななかタンザニア行きのお知らせが。ご主人は青年海外協力隊のご経験があり、奥様も国際的なお仕事に携わっておられる由、なるほどと思うものの、やはり驚きです。
実は私、20代はじめの頃、青年海外協力隊の説明会に出かけたことがあります。当時、安定した会社員生活を送っていたのですが、なにか飽き足りないものを感じていたのでしょう。あれこれ模索していた時期でした。
たまたま見かけた案内のポスターにつられ出かけたものの、そんな甘い考えは開始数分で打ち砕かれました。私はその地で役立つ技術も資格もなにひとつ持ち合わせていませんでした。自分の無力さと甘さを痛感し、その場にいることすら恥ずかしかったことを覚えています。
その後も電車の中などでポスターをを見かけるたびに、あの時の情けなさが蘇ります。そして、いつからか目につくようになったのが、青年海外協力隊と共に併記されるシニア海外ボランティアの募集案内でした。
結婚後、二人の子供が小学校に上がったのを機に服飾の専門学校に通い、卒業後はささやかながらニットのお仕事をさせてもらうようになっていました(ブログ杉本先生から教わったこと)。今なら、現地の女性に編み物の技術を伝えられるんじゃないか。木綿の糸などで日用品や簡単な衣料を作れたら、女性の自立の助けになるかもしれない。そんな夢を描くことも。
けれど今の自分の置かれた状況では、とうてい叶わない夢だと諦め、それもまた体のいい言い訳に過ぎないと、覚悟も行動力もない自分がやっぱり恥ずかしくなり。
そんな私をよそに、この間どれだけの若者やシニアの方たちが各国に赴き、活躍してこられたのでしょう。そうした若者のお一人が、家庭を持ち、今度はご家族で新たな夢を追いかけられる。本当に素晴らしいことだと思います。
現地到着後、フェイスブックに初めてアップされた投稿には、ねねちゃんが黒人の男の子と仲良く手をつなぎ、楽しげな表情で立つ写真が添えられていました。京都弁でコミュニケーションを取っているとのこと。たくましい!(笑)
タンザニアで暮らすこと。その地で新しいものを根付かせること。大変なことだと思います。ましてや小さな子供さんを連れての赴任には、数々の不安もおありだったでしょう。その一つ一つを超える意義を感じての決断だったのだろうと推察します。
そんな不安をよそに、ねねちゃんはねねちゃんなりの役割をしっかり果たしている様子。どんな女の子に、女性に成長していくのでしょう。ねねちゃんと似た波長を持っているであろう私は、とても楽しみに思っています。
お陰様で、私もようやくがんばれる場所が見つかりました。海外の途上国ではなく、ここ寺町に。「しののめ寺町」も新体制で新年をスタートしたばかり。緊張して過ごした一ヶ月でした。どこからやって来たのか、こんな言葉がしきりに浮かぶ一ヶ月でもありました。
不安は希望を孕(はら)んでいる。
店に立ちながら、時々タンザニアに思いを馳せています。タンザニアに友達がいる。空を見上げれば、空はひと続き。まずは健康第一に、地道に進んでいかれることを祈るばかりです。
参考までに関連のリンクを貼らせていただきます。ぜひご覧ください。
https://www.facebook.com/mitsuru.goshozono/posts/723893977710327?pnref=story