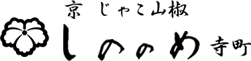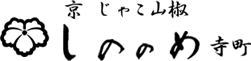家事
家のこと
2016年07月25日

店を始めて以来、ずいぶんと生活が変わりました。なにが変わったといって一番変わったこと、それは自宅にほとんどいなくなったことではないでしょうか。営業時間は10時から6時。準備と後片付けの時間を合わせると、一日の大半を店で過ごす毎日です。そうして困るのが、家事をする時間がなくなったこと。
このブログを読んでくださっている皆さん、そもそも「家事」と聞いてどんなイメージを描かれるでしょうか? 男女で、年齢で、人によって、状況によって、ずいぶん違うのではと想像します。
家事って、決まったパターンのある、基本的な、普遍的な、そういう作業のように思われますが、本当にそうでしょうか。マニュアルがあるでなし、業務規則があるでなし、誰かに査定されるでなし。すべては本人の資質に委ねられた、とても流動的な、個人的な、そうした作業だと思います。
長年「ほぼ専業主婦」だった私の場合…。家が文字通りの「ホーム」。朝、目覚めてから、夜、寝付くまで、いつも家が中心。衣食住すべてに関わる家事一切が私の仕事と思っていました。
主婦の身で専門学校に通ったり(ブログ杉本先生から教わったこと)、少しばかりの仕事をする時期もありましたが、そんな時も家事は欠くことのできない仕事として、いつも私の中心に位置づけられていたように思います。
やってもやっても尽きない仕事は、まるで賽の河原で石を積むよう。スキルを上げたとて、誰から評価されるでなし。閉ざされた世界で、自己満足で終わることしばしば。決して楽ではない、それはそれは地味な作業です。
そんな家事を、好きというわけではないけれど、さして嫌いでもなく、当たり前のこととして毎日せっせと、いそしんでいました。今になってみると、よくやっていたなぁと、あの頃の自分に声を掛けてやりたい思いです。
「しののめ寺町」開店と共に、生活の中心が自宅から店へ。家事から商売に。一転、こちらは開かれた世界。評判や売り上げという形で、すぐに結果が表れます。やはり店優先、家事はあとまわしの生活になりました。
手を抜いたり、省略したり。それなりにやり過ごせるものだなぁと思う反面、なにかしら豊かさに欠ける生活になったなぁと感じることも。家事の果たす役割の大きさを再認識しています。
ときに面倒に思うこともあった家事ですが、十分にできなくなってみると、あら不思議。できないことが、今、とてもストレスになっています。
曇った鏡を見ると、心まで曇ります。いい加減な料理で食事を済ませていると、心まで貧しくなるような。着飾って出かけても、帰ってきた部屋が雑然としていると、そういう私ってイケてないなぁと思います。
思いっきり、家事をしたぁ~い。
もし10日間の休みがあったとしたら…。旅行より、遊びより、家事! 家中どこもかしこもピカピカに磨き上げ、タンスの中から引き出しの中からスッキリ整理して。そうして、食事時にはテーブルいっぱいの手料理を並べ…。
そんな妄想をしている自分がいます。現実に叶ったら、やってられないよぉ~と、3日で音を上げること間違いなしですが(笑)。
10日間とはいきませんが、休みの日、たまった家事をやっていると、心が穏やかになっていく自分に気づくことがあります。部屋がきれいになると、空気が入れ替わり、呼吸まで楽になるような。用事が片付くごとに、心の中まで整理されていくような。家事は心身と密接につながっています。
長年やってきた家事のあれこれ、店をやっていくなかで役立っていることも、たくさんあります。家事はあらゆる感性を駆使して行う、とてもクリエイティブな作業だったのだなぁと思います。
家事って素晴らしい!
家事をうまくこなせる人は、きっと仕事もデキるはず。ただ、悲しいかな、その両立は難しい。家事の得意な女性たちが社会で活躍できるようになれば、様々な仕事の現場は、今と少し違ったものになると思うのですが。
家事というものが、もっと評価されること。男性であれ、女性であれ、仕事と家事の両立に悩まされることなく、誰もが生き生きと働ける世の中になること。願いです。
もはやかつてのような家事はできないけれど、要領よくこなせる術を身に着けたい。そうして、心身ともに健やかに、穏やかに過ごしていたい。お中元時期忙しく、ますます家事がおろそかになってしまったこのごろ。そんなことを思う私でありました。
何必館の時間
アートなこと
2016年06月23日

店をやっていてよかったなぁと思うことはたくさんあります。一方で、大変だなぁと思うこともいくつか…。そのひとつが、止まれないこと。
たまには少し立ち止まりたいと思うことがあります。一旦、立ち止まって、いろんなことをゆっくり考えてみたい。そうして、いろんなことを整理してみたい。目に見えるものも、見えないものも。
あるいは、しばらくの間、なぁんにも考えないで過ごしてみたい。懸案事項をすべて棚上げにして、頭の中を空っぽにして、ぼぉ~っと一ヶ月、せめて二週間、いえ一週間…。そんなことをしきりに思うこのごろ。
現実は、店を始めたが最後、そんなことは言っていられません。よくよくわかっていながら、それでも頭をかすめる思い。それはそれで大切なサインなのかも。ダウンしてしまった昨年の夏を思い出し(ブログユルスナールの靴2)、自分の心身に注意を払うよう心がけているところです。
そんななか、月に一度の連休は、それはそれは楽しみな二日間です。どうやって過ごそうかと、早くからあれこれ考えます。まずは一ヶ月の間にたまった心と体の疲れを取ることが最優先。
次に、しなければいけないこと、したいことをピックアップ。挙げ出すときりがなく、とてもじゃないけれど二日間に収まりそうにありません。優先順位の上位いくつかを選び、段取りよくことが運ぶよう、時系列でメモに書き留めておくことが習慣になりました。
そうまでして立てた綿密なタイムスケジュールも、当日になって過密過ぎることに気づくことたびたびです。ああでもない、こうでもないと、組み換えたり、端折ったり。そんなことに要らぬ時間を費やしていたりして。まったくもって、なにをやってるんだか(笑)。
今月第二週の連休は、仕事がらみも含めて、いつにも増して過密なスケジュールになっていました。二日目の朝、どうにもこなせない自分に気づきました。その日の予定で、気持ちの向くもの、向かないもの、自分に問うてみることに。
当初は余裕があれば行きたいなぁ、くらいに思っていたことが筆頭に挙がりました。何必館・京都現代美術館で開催中の「サラ・ムーン展」。大好きな写真家の展覧会です。http://www.kahitsukan.or.jp/
もう十年以上前、初めて出かけたサラ・ムーンの展覧会でのこと。たまたまフロアに私一人。見るほどに怖くて、美しい彼女の写真。その中に思わず引き込まれそうな感覚に、鳥肌が立ったのを覚えています。
その日の予定の中から、この展覧会を一番に選んだことに、至極、納得する自分がいました。今日はのんびりモードに切り替え、自分がしたいと思うことだけをして過ごそう。そう決めました。
期待通りの展覧会に満足し、最後は最上階の坪庭前のソファで一息つくのが、何必館での私のお約束です。天窓から注ぐ光と風に、刻々と変わる木の陰影。祇園の真ん中とは思えない静寂の空間。自分の呼吸まで聞こえてくるようです。
あぁ、時間が止まってる…。
同じ時間でも、あっという間に思うこともあれば、長く感じることもあります。
時間はいつも刻々と流れているようで、実は時に早く、時にゆっくり、自在に、気まぐれに流れている。そう思うことがあります(ブログ休日)。何必館で過ごした時間は、まるで止まっているようでした。
毎日、忙しいのは間違いないけれど、自分が思うよりずっと時間は自由なものなのかもしれない。時間に枠をはめ、そこに自分を押し込んでいたのは、私自身ではなかったか。
楽しい時も、しんどい時も、そのときどきの時間を愛おしみながら過ごしていきたい。自分の心の声に耳を傾けながら…。それが、かけがえのない私の人生の最高の過ごし方。
風に揺らぐ影を眺めながら、そんなことを思ったひととき。わずかの時間でも、立ち止まれた気がしました。
鳳凰様
お祭りのこと
2016年05月30日

去る5月22日、店近くの氏神様、下御霊神社のお祭りが今年も盛大に行われました。寺町に店を構えて四年。開店からの年数を数えながら、そのときどきの思いも蘇る一日。私にとって、お祭りはとても大切な節目の日となりました(ブログお祭りの夜に 夢見通りの人々)。
その日は、朝から夏を思わせる厳しい暑さでした。長い距離を巡幸し、夕刻、神社に戻ってきた御神輿。男衆さんたちの日焼けした顔に、道中の大変さが忍ばれます。それでも皆さん、晴れやかな笑顔。お祭りの高揚感が伝わります。
神社前まで来ると、いよいよクライマックス。宮入前の差し上げです。御神輿の上には黄金の鳳凰が載せられています。御神輿に合わせて、尾羽がカシャカシャと音を立てて揺れ、今にも飛び立ちそう。
実は店を始める前、とても信頼を寄せている方から、私のガイドをしてくれるのは鳳凰だと聞かされたことがあります。困った時には、鳳凰にお願いするといいとのこと。そのあと鳳凰の置物を高額で売りつけられた、なんてことは、もちろんありません。念のため(笑)。
鳳凰と聞いてまず浮かぶのは、宇治の平等院でしょうか。空を背景に浮かぶ、鳳凰堂の屋根のシルエットは、あまりに美しい。鳳凰が私のガイドって…。不思議な気持ちですが、以来、私の中で鳳凰は特別なものになりました。
絵でも写真でも、なにか身近に持っていたいと思っていたところ、毎月、東寺で開かれる弘法市で、偶然にも鳳凰の香炉を見つけました。迷わず買い求め、開店以来、店に置いています。いつも守ってもらっているよう。閉店後、ありがとうございますと、お腹のあたりを撫でて帰るのが毎日の習慣です。
ある日、こんな夢を見ました。見上げるときれいな青空。一面に白いうろこ雲。見る間に、細かな雲が羽を広げた鳳凰を形作っていきました。よく見ると、雲で描かれた鳳凰が、右に左に、上に下に、何羽も折り重なるように、空一面を覆い尽くしています。この世のものとは思えない美しさ、神々しさに、ただただ見とれる私。 夢はたちまち忘れるものですが、この夢は今も鮮明に覚えています。アートのような映像も、その時の心の震えも。
もともと空を眺めるのが大好きな私。店でも暇な時間、外に出ては空を見上げることがよくあります。詰めていた息が、ふぅっと解かれるよう。その空に、夢で見た鳳凰が浮かびます。しばし目を閉じて、心の中で手を合わせることも。いつからか鳳凰様と呼んで、祈る対象になりました。
神社前で、いよいよ最後の差し上げの時。空高く掲げられる御神輿を眺めながら、私の中に感動と共に、あるひらめきが浮かびました。 私は鳳凰様に導かれ、この地にやってきたんだ。鳳凰様に守られ、今日まで店を続けてこられたんだ。私のガイドをしてくれていたのは、あぁ、確かに鳳凰様だったんだ。 鳳凰様は私の神様…。
去年のお祭りの日に漠然と感じた思いが、今年、確信に変わりました(ブログ下御霊神社)。 来年もこの場所で、お祭りを楽しんでいる私がいますように。また一年、がんばります。だから、鳳凰様もどうか私を守っていてください。畏れ多くも、鳳凰様とそんな約束を交わした今年のお祭りでした。 
エネルギー
心と体のこと
2016年05月18日

1月から新しい体制で始動した今年。当初は精神的緊張が高く、その疲れが大きかったように思います。気づけば5月も半ば。今度は体の疲れを自覚するようになってきました。
店にいる時間が長くなり、慣れない業務も増え、当然といえば当然の結果。自分の体は自分で管理しなければと、改めて反省しきりです。そんなことを思うのも、心に余裕ができてきた証拠かなと、少しほっとする気持ちにもなったり。
自分の心と体に思いを寄せながら、ひとの持つエネルギーについて考えるこのごろです。
店を始めるにあたって心配なことは山ほどありましたが、なんといっても一番の心配は、体がもつかということでした。なにしろスタミナのない私。疲れは慢性的に感じてきましたが、お蔭様で店を休むほどのことは一度もなく、今日までやってこられました。以前の私を思うと、信じられない思いです。
それなりに体調に気を配ってきたせいもあるでしょうが、決してそれだけではなかったような。自分のやりたいこと、やるべきことが見つかり、自分の持っていたエネルギーがやっと動き始めた。そのエネルギーに突き動かされてやってこられた。そう思っています(ブログ ユルスナールの靴 ユルスナールの靴2)。
エネルギーは人が生きていくための力の源。このエネルギーの使い方次第で、人生が決まるのでは、と思うほどです。
なんにつけ計算のできない私は、このエネルギーの配分がとても下手。知らぬ間に使い果たし、気づいた時には枯渇状態。なんてことが何度かありました。全力疾走しては倒れ込むタイプです。そんな時は、否が応でも補給に専念するしかありません(ブログ 私の心の中の瓶)。
持てるエネルギーを酷使して向う見ずにやってきましたが、それでは通用しない時が来ているような。今のエネルギー量では手に負えない。もっと大きなエネルギーがほしい。最近、切にそう思うようになりました。
自動車のように、搭載エンジンを積み替え、簡単にパワーアップできたらどんなにいいでしょう。人間はそう簡単にはいきません。
自分が持っているエネルギーを、うまく活用するしかなさそうです。まだ眠っているエネルギーがあるなら、それを目覚めさせてみる。すでに動いているエネルギーは、もっとうまく巡らせてみる。そのためによさそうなことを、少しずつ実践しているところです。
たとえば…。エネルギーを活性化させてくれそうなものに触れてみる。物であれ、人であれ、場所であれ。刺激を受けたり、ワクワクしたりして、エネルギーが自ら元気に動き始めるように。
たとえば…。疲れた時には、そっと癒してくれそうなものに寄り添ってみる。そばに置くだけで心安らぐ物だったり。一緒にいるだけで安心できる人だったり。そこに居るだけで心和む場所だったり。疲れたエネルギーが静かに回復していくように。
エネルギーを元気づけたり、慰めてくれるものを、身の回りにたくさん見つけておくことは、とても大切だなぁと思います。
限られたエネルギーを、つまらぬことで消耗させない。価値あることにこそ使う。というのも心掛けたいことです。エコの精神ですね。
時には、私がエネルギーを操作するのではなく、エネルギーの赴くままに身を委ねてみる、なんていうのもおもしろいかも。予想外のことが起こりそう。
エネルギーと仲良く付き合っていくことは、人生そのものが豊かになっていくこと。やがてエネルギーが心強い味方となって、私をけん引していってくれたら…。
持てるエネルギーをフルに使って、人生を生き切りたい。
新緑の持つエネルギーに触発されたからでしょうか。そんなことを思う五月。まだまだスタミナ不足の私ですが、少しずつ増強を図っていきたいと思っています。どうぞ気長にお付き合いくださいますようお願いします。
日常
心と体のこと
2016年04月29日

熊本で大きな地震が起きました。お客様の中にも熊本にお住まいの方がおられ、心配しているところです。
世界で、日本各地で繰り返される災害には、自然の恐ろしさを感じずにはおれません。なかでも地震は、人の手で作られた街に住んでいるようで、実は地球という星に住んでいるに他ならないことを痛感させられます。
日常と思っている日々の暮らしが、決して常なるものではないこと。平凡だったり、時につまらなく思える日常が、実はかけがえのないものであること。災害や事件、事故の映像を目にするたびに思い知らされます。
先だっては、知人が大きなアクシデントで急死されるという出来事がありました。テレビのニュースで知った時の驚きは、今までに経験したことのないものでした。ご家族の嘆きはいかばかりか。日常というものについて、考えることの多いこのごろです。
店を始めて、それ以前にも増して、大小様々なことが起こる生活となりました。開店時間に店を開け、閉店時間に店を閉める。当たり前に思えるそんなことが、決して当たり前でないこと。滞ることなく繰り返していかれる毎日が、どんなに有り難いことか、身に沁みてわかるようになりました。そうして積み上げられた一日一日が、先だって迎えた開店四周年です。
有り難く思いながらも、慌ただしさばかりが先行していたこれまで。最近になって、ようやく少し余裕が生まれてきたのでしょうか。こうした日常に心を向ける時間が、わずかですが持てるようになってきました。
災害も、事件も事故も、明日は我が身。そうしたことに遭遇しないまでも、生老病死はひとの常。今日の日常が明日も続く保証など、誰にもありません。もちろん不老不死など望むべくもない。
そんな貴重な今日を、過去を悔やんだり、未来を憂えて過ごしていてはもったいない。運命づけられたこと、努力ではどうにもならないこと、そんなことを恨んだり、嘆いたりしていてもしようがない。
し残してきたことを悔いるより、してきたことに誇りを持とう。自分に欠けているものを数えるのではなく、自分に備わっているものに目を向けてみよう。今、ここにある、あるがままの自分。あるがままの現実。まずはそれを認めてみよう。そう思うようになりました。とても難しいこと。簡単にはいきませんが。
近頃、今までと変わらない日常が、少し違って見えてくるようになりました。なんでもない日常にも、小さな喜びが見え隠れしています。それを見つけられるか見過ごすか。すくい取れるか、取りこぼすか。その差はほんのわずかだけれど、人生の楽しさは大きく違ってくるように思います。
日常を大切に思うことは、とりもなおさず自分を大切に思うこと。今という時を愛おしみ、今ある自分を愛おしむ。それが、今、私の思う「日常」。
熊本の地震で犠牲になられた皆様のご冥福を祈ると共に、一日も早い復旧を願いつつ、私もがんばっていこうと思っています。
なおゴールデンウィークは、5月4日(水・祝)が営業。5月5日(木・祝)が休業となります。お間違えのないよう、よろしくお願いします。